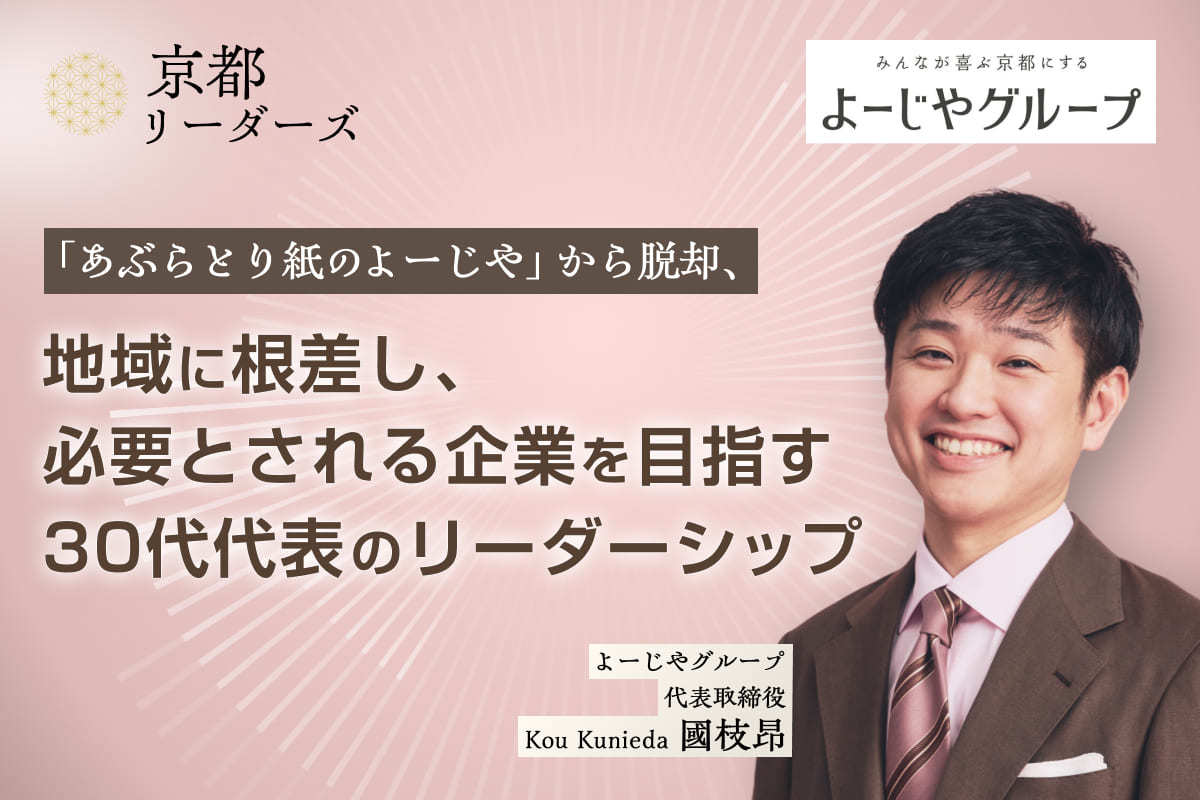
創業120年を超える老舗「よーじや」は、コロナ禍で、一部の店舗で売り上げの97%を失うほどの危機に直面した。就任直後にそれだけの困難に直面した國枝代表は、それまでの、よーじやといえば「あぶらとり紙」、観光客向けというイメージを刷新し、京都に住み働く人々にとって不可欠な企業となるべく、抜本的な変革を進めてきた。その一つがスポーツチームへのスポンサードだといい、自ら足繁くスポンサードするチームの試合に駆けつけている。そんな國枝代表の、変革の背景にある経営哲学、京都の未来への貢献にかける熱い想いとは──。
就任半年でコロナ禍突入、「よーじや=あぶらとり紙」というイメージからの脱却
── 御社は長い歴史のある、あぶらとり紙という看板商品のある老舗ですが、そうしたイメージからの脱却を図っているとか。
國枝 よーじやは創業120年を超える老舗ですが、京都にはさらに長い歴史を持つ企業も多く、その中で当社の立ち位置をどうとらえるかは、ずっと課題です。特に「よーじやといえばあぶらとり紙」というイメージと、私たちが目指す姿との間に乖離があると感じ、この6年間で方向性を大きく変えてきました。
あぶらとり紙は創業当初からの看板商品ではなく、約35年前にブームとなり広く知られるようになりました。よーじやという屋号は、当時は楊枝と呼ばれていた歯ブラシのこと。それまでの八十数年間は、日用品を買うお店として地元に愛される形で、2店舗ほどで営業してきました。あぶらとり紙のブームでイメージが定着し、地元の方々だけでなく観光客の方々にも支えられるようになったのです。
しかし、2015年頃からインバウンドが増加し、私が2019年8月に就任した半年後にはコロナ禍に見舞われました。売り上げが97%ほど減る月もあり、あぶらとり紙の売り上げもコロナ禍以前から4分の1以下に落ち込んでいました。これは、あぶらとり紙が「過去のもの」「お土産品」として認識され、生活必需品としての役割を失っていたことを浮き彫りにしました。
我々がこれから取り組むべきは、観光客だけでなく、京都に住み、働く方々にとって必要な会社となることです。
──コロナ禍直前に代表に就任され、大変な状況下で新しい軸を打ち出しての変革は大変だったかと思います。どのように進められたのでしょうか。
國枝 大きな方向性を変える点については、会社の代表者として、私自身がリーダーシップを取り、社員に伝えてきました。ただ重要なのは、社員がいかに大枠の方向性を理解してくれるかです。私一人で業務のすべてに関わることは現実的ではないからです。理解が広がれば、細かいことについては各部署に権限を委譲して進められます。
現在、よーじやに入社する社員は、観光業としてではなく、「京都にどう貢献できるか」という方向を向いていることを理解したうえで入社してくれています。
世間はまだ、よーじやを観光業、あぶらとり紙の会社というイメージでとらえているかもしれませんが、社内の人間はほぼすべてが今の方向性を理解してくれています。
── 今の方向性に至るまで、どのように思考を深められたのでしょうか?
國枝 物事を考えるうえで、自身の直感を非常に大切にしています。意思決定をする際の選択肢は2つあり、それは他人のアドバイスと自身の直感だと思います。
現在のよーじやの方向性は、先人を含め多くの人が選ばなかった道を進んでいるという自覚があります。
なぜこの方向へ舵を切ったかというと、今の立場になってさまざまな人と話し、多くの情報を得た中で、(就任したころは)「よーじやは愛されていない」という確信を持ったからです。
経営者という立場では、無責任な、データに基づかないアドバイスを受ける機会が非常に多いのですが、単なるイメージを根拠にした、「よーじやは京都に貢献してきた」という言説に流されず、自分自身の直感と信念を大切にできる環境をいかに作るかにこだわってきました。
よーじやの強みは、ある意味「一匹狼」としてやってきた、ありそうでなかった会社である点です。自分自身の感覚と意思決定に責任を持てる環境を貫いてきたことが、他の企業にはない強みだと考えています。
過去してこなかった新規出店に積極的な理由
── 現在、特に力を入れている事業や活動について、具体的に教えていただけますか。
國枝 直近で申し上げると、商品ラインアップと販路の抜本的な変革です。販路については、これまで観光地以外での新規出店がほとんどありませんでしたが、最近では大阪の心斎橋や梅田、東京の北千住、札幌など、京都以外での出店を積極的に進めています。
これは、「京都に来て、よーじやを知って、買っていただく」という従来のスタンスでは通用しないと考えているからです。お客様に「よーじや自体を好きになっていただく」ための受け皿を、私たち自身で作っていく努力をしています。
商品開発では、以前は観光シーズンを意識した季節限定商品が目立っていましたが、現在は毎月のように新商品を開発しています。
先日発表したクリスマスコフレには、「これをよーじやが作ったとは思えない」という意外な反応が多く寄せられました。これは、お客様が抱く「よーじやらしさ」にとらわれず、今の時代に求められるものを追求する体制を強化している結果です。

こうした努力が実を結び、かつて観光シーズンと閑散期で2.5倍もの売り上げ差があった状況が改善されつつあります。
京都の観光地はオーバーツーリズムのイメージがあるかもしれませんが、清水や嵐山などでは前年同月比で30%ほど売り上げが減少している店舗もあります。しかし、よーじや全体の売り上げは20%増となっており、これは5年前から掲げてきた二つの方向性が奏功している証だと感じています。
── 東京の北千住への出店は、新宿や渋谷といった繁華街ではなく、下町だという点が印象的です。この出店の意図についてお聞かせください。
國枝 複数店舗を展開するうえで、インバウンドが溢れる地域、たとえば銀座などへの出店は、私たちの方向性とは明確に異なります。

私たちが伝えたかったのは「お店の周辺に住む方々に、身近に感じてもらえる店を作りたい」という意図です。北千住の店舗は足立区民のリピーターがほとんどで、私たちの商品開発や店舗運営の努力が結果に反映されやすい場所です。
インバウンドは短期的な売り上げにはつながりますが、外部要因のリスクが高いです。数十年スパンで考えた時、日本のお客様を向いた商売展開をしなければ足元をすくわれる可能性があります。だからこそ、地元や日本人のお客様を意識した出店を重視しました。北千住駅は乗降者数も世界トップ10に入るほど多く、イメージ戦略だけでなく、デベロッパーの理解も得て出店に至りました。もちろん銀座への出店の可能性もありますが、最初に選ぶエリアとしては観光客の多いエリア以外が適切と考えました。
社員のモチベーションを下げないための心がけ
── コロナ禍で売り上げが90%以上減少したこともあったそうですが、社員のモチベーションをどのように維持されたのでしょうか。リーダーとして心がけられたことをお聞かせください。
國枝 就任して半年後にコロナ禍に見舞われ、現実的にはがむしゃらにやっていましたが、心がけていたのは、ネガティブな発言や不安を口にしないことです。
よーじやの経営陣や幹部は、あぶらとり紙のブーム以降に入社した者がほとんどで、数字を見る意識が希薄でした。「放っておいても儲かる」という前提・思い込みがあったため、あぶらとり紙の売り上げが4分の1に落ち込んでも危機感がありませんでした。社員が一番危機感を持っていなかったかもしれません。
ただそこで、変に危機感を植え付けるようなことはしませんでした。
当時、多くの企業が給与カットを余儀なくされる中、当社は従業員の給与を100%保証すると最初から伝えていました。ボーナスは厳しい状況でしたが、従業員の給与カットはせずにここまで来られたことが、一体感につながったと感じています。
── 新しいメンバーは、会社の新しい方針を理解したうえで入社されているとのことですが、採用の際に重視されている資質や考え方はありますか。
國枝 会社方針を理解し、それに対してワクワクしたり、共感したりしてくれるかというマッチングの重要性を常に伝えています。同じ方向を向いて進めることが大切だからです。
もう一つは「協調性」です。主観や自身の考えを持つことは素晴らしいですが、時には他者の意見を排除するリスクを高めることもあります。協調性に関しては、他人と一緒に物事を進める力が非常に重要だと考えています。

現在、社員は200人近くいますが、今後300人、400人と増えていく中で、複数の人間が関わって物事を進めることは避けられません。一人の突出以上に、複数人で進める力が大切です。
── 協調性を重視すると、周りの意見をうかがいすぎる、悪く言えば「忖度」が強くなる心配はありませんか。
國枝 その懸念はあります。だからこそ、私自身の立ち位置は今後も変化させていかなければならないと考えています。
私が目立つ会社ではありますが、社内のことについては従業員が自立して動ける体制に持っていく必要があります。ある程度話し合える環境が整えば、そうした懸念は排除できる部分も多いでしょう。私自身の役割と、私以外の社員の役割を明確に区別していくことが重要です。
うまくいけばいくほど難しさを感じますが、業務遂行における私の依存度を下げ、まだ生み出されていないことに関して私自身が力を発揮する。つまり、外に向けて活動していくことが、私の仕事だと日々感じています。
「京都の未来を変えること」に貢献するという選択
──京都に拠点を置く企業として、京都という土地にどのような可能性や課題を感じていらっしゃいますか。
國枝 私は幼少期に、よーじやが組織として京都に貢献できていないという複雑な思いを抱いて過ごしてきました。先代の貢献を知らないまま経営者になったため、良くも悪くも先代の影響を受けずに、自身の信念で意思決定できる環境を築けたのは強みです。一方で、一匹狼以外の選択肢を持たないことが弱みでもあり、京都との向き合い方には悩んできました。
伝統行事に多くの企業が関わる中で、よーじやはこれまでそうした関わりが希薄でした。そこで考えたのが、「これからの未来の京都を変えていくことに尽力する」という貢献の形です。120年企業のトップでありながら30代で経営を担うという強みを活かし、まだ課題として認識されていないことに対して取り組むことが重要だと考えています。
他府県の方からは、京都の老舗経営者であることをうらやましがられます。「京都は素晴らしい、これからも大切にしてください」と言われますが、観光業が観光を追求し続けた結果、京都が「住む」場所としては遠い街になってしまうのではないかという違和感があります。
たとえば、プロスポーツの盛り上がりと人口が比例していない点もそうです。京都ハンナリーズや京都サンガF.C.のスポンサーを務めているのは、こうした違和感を解消し、スポーツの盛り上がりに貢献したいという思いからです。
今後は、オーバーツーリズムや京都市内外の格差問題など、京都が抱えるさまざまな課題を念頭に置きながら、事業を進めていきたいと考えています。
── 京都の他のリーダーで、尊敬されている方はいらっしゃいますか。
國枝 京都ハンナリーズのビールも作られている、ローカルフラッグ代表の濱田祐太さんです。彼の「化け物級の行動力」には驚かされました。私は人見知りなタイプで、自分から積極的に話しかけることは苦手なのですが、彼を見て、若さや知名度に関係なく、さまざまな方と話せるのだと気づかされ、自分自身も変わることができました。
彼はベンチャー企業の強みである行動力と、老舗企業のようなバランス感覚をあわせ持っています。私は「正解が一択である」という考え方が嫌いです。自分自身の性格を理解し、最適なやり方を見つけて行動することが重要だと個人的には思っています。
濱田さんのように、ベンチャーでありながらベンチャーではない人たちも受け入れられる「器の大きさ」は、私自身も持ち合わせるべきだと感じました。彼を見て、年下に対して初めてリスペクトできたかもしれません。
「あぶらとり紙でおなじみ」という枕詞を消す
── 今後の展望についてお聞かせください。
國枝 私の代で確実に成し遂げたいのは、「あぶらとり紙でおなじみの」という枕詞を消すことです。これは、あぶらとり紙以外のイメージをしっかりと確立していくことを意味します。イメージがなくなれば終わりですから、その入れ替えをいかにスムーズに行うかが課題です。
そのために必要なのは、他社がやっていない「未来の京都」に貢献しているというイメージを、京都に住む方々を含め、あらゆる方々に持っていただけるかどうかです。
既存のよーじやブランドだけでなく、新しいブランドの成功も必須だと考えています。よーじやはこれからも観光客の受け皿であり続けますし、その努力も続けます。よーじや自体もライフスタイルブランドとして幅を広げることを目指しますが、京都への貢献という点では、よーじやというブランドだけでは限界があると思っています。
あぶらとり紙のイメージを良い意味で消し、京都に貢献しているという強い意志を持って、来年発表を目指して準備している新規事業を形にしていきます。自社利益の追求だけではない形で存在できれば、あらゆる観点で「よーじやといえば京都に欠かせない会社だよね」と思っていただけるはずです。
任天堂さんを京都の人々が誇りに思うように、規模は違えど、50年、100年経った時に、よーじやが京都に欠かせない企業だと思っていただけるような姿勢を貫いていきたいです。
── スポンサー活動を続ける意味やメリットについてはどうお考えですか?
國枝 スポンサーメリットを最も享受しているのは、よーじやだと感じています。特に京都サンガF.C.や京都ハンナリーズのスポンサー活動を通じて、大きく変わりました。
私は営業が得意ではありませんが、共感を呼ぶのは得意だと感じています。自分のために頑張る姿勢は相手に気づかれてしまいますが、真剣に応援する姿勢は伝わります。サンガのスポンサー企業は何百社もありますが、よーじやが最も応援している企業、そして最も応援している経営者だとサポーターの方々に感じていただけているのではないかということが一番大きいと感じています。

昨年はサンガの試合に37試合行きました。アウェー戦はすべてゴール裏で応援し、ユニフォームを着用し、応援歌もすべて歌います。日程確保はたいへんですが、そこまでして応援しているからこそ、サポーターに伝わるのだと思います。
「うちの商品を買ってください」と直接言う営業力やマーケティング力も重要ですが、一歩回り道をして「応援する」というルートを挟むことで、結果的に応援してもらえるという、回り道のようで必要なルートがあるのです。
社員が直接営業せずとも、サンガやハンナリーズを応援する方々がよーじやの商品を買ってくださる流れが生まれているのは、私たちが真剣に応援していることが伝わっているからだと確信しています。
このスポンサー活動は「三方よし」の考え方にも通じます。売り手、買い手だけでなく、世間や第三者を意識しながら事業を進めることで、短期的には正解でなくても、10年後には安定的な関係性を構築するという長期的な正解につながります。営業力、マーケティング、ブランディング以外の要素をいかに考えながら実践していくか、これを常に意識しています。
